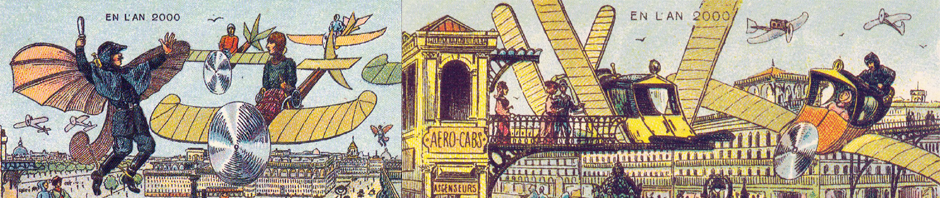- 塚本芳和•和久井孝太•堀之内勝一(1996)『電子メディアの近代史ー「井戸を掘った人々」の創造と挑戦の日々』ニューメディア
「電子メディアはハイテク産業ですから、技術の進歩が新しい機器を創り、新しいニーズを生み、そして新しい方式を作りだすという関係が繰り返されしかもそれが次第に早いテンポで進んでいき、新しいメディアが開発•実用化され、普及・発展しています。そこで、電子メディアの歴史を総括するには、放送•通信•コンピュータや周辺技術がどのように創られ、実用化されていったかという「技術」の歴史がその中心となります。
一方、技術がいかに優れていても、日本の中でメディアとして育つとは限りません。メディアとして成立していくには、日本の風土に合ったものでなければなりません。その場合、大きな制約を与える日本の文化や制度があります。日本はアメリカとは違い官主導の国ですから特にこの点が重要です。そこで、放送•通信•コンピュータ産業の育成・発展に大きく関与した諸制度が創られた時代背景と、制度の変遷について記録することは貴重な財産となります。
さらに、経営•ビジネスの課題を浮き彫りにするには、トップリーダーたちが、ビジネスの観点から先見性をもってチャレンジし、多くの苦難に打ち勝って、産業の基盤を創った足跡をたどることが必要です。
また、個別のメディアサービスを、画に描いたモチではなく、具体化をはかり、創意工夫をこらし、世の中に普及•定着させた現場のクリエーティブ・ワークに従事した幅広い分野の人々が辿った試行錯誤のプロセスから、時代を切り開いた人々の知恵と努力の成果に光を当てることにしました。」(p.3)という考え方のもと、「技術をタテ糸とし、制度•経営•ビジネスをヨコ糸として、電子メディアの歴史を織るにあたって、 第一線で活躍した人々に直接インタビューを行い、その方々の証言をもとに、「電子メデイア」の発展の過程を検証し、歴史としてまとめ」(pp.3-4)た書籍
一方、技術がいかに優れていても、日本の中でメディアとして育つとは限りません。メディアとして成立していくには、日本の風土に合ったものでなければなりません。その場合、大きな制約を与える日本の文化や制度があります。日本はアメリカとは違い官主導の国ですから特にこの点が重要です。そこで、放送•通信•コンピュータ産業の育成・発展に大きく関与した諸制度が創られた時代背景と、制度の変遷について記録することは貴重な財産となります。
さらに、経営•ビジネスの課題を浮き彫りにするには、トップリーダーたちが、ビジネスの観点から先見性をもってチャレンジし、多くの苦難に打ち勝って、産業の基盤を創った足跡をたどることが必要です。
また、個別のメディアサービスを、画に描いたモチではなく、具体化をはかり、創意工夫をこらし、世の中に普及•定着させた現場のクリエーティブ・ワークに従事した幅広い分野の人々が辿った試行錯誤のプロセスから、時代を切り開いた人々の知恵と努力の成果に光を当てることにしました。」(p.3)という考え方のもと、「技術をタテ糸とし、制度•経営•ビジネスをヨコ糸として、電子メディアの歴史を織るにあたって、 第一線で活躍した人々に直接インタビューを行い、その方々の証言をもとに、「電子メデイア」の発展の過程を検証し、歴史としてまとめ」(pp.3-4)た書籍
| 第1章 放送・通信・コンピュータの歩み [塚本芳和] | |
| 日本の戦後はラジオから | |
| 高度経済成長期を背景に急成長したテレビ | |
| 衛星時代とメディアの多様化 | |
| 通信の自由化とコンピュータ産業の発展 | |
| グローバル化とマルチメディア化 | |
| 現状と今後の行方 | |
| 第2章 放送事業総論 | |
| 網島毅 | 戦後電波行政のレールを敷いた男 |
| 塩野宏 | 放送法制度研究の第一人者 |
| 川口幹夫 | ハイビジョンの名付け親 |
| 中川順 | テレビ東京「中興の祖」 |
| 志賀信夫 | 日本に放送批評を確立 |
| 木暮剛平 | 「広告の鬼」吉田秀雄の愛弟子 |
| 第3章 放送経営 | |
| 島桂次 | NHKの報道を確立した男 |
| 北川信 | 民放生え抜きの大プロデューサー |
| 磯崎洋三 | 民放の雄「TBS」の名編成マン |
| 日枝久 | テレビを楽しくした張本人 |
| 佐伯晋 | 朝日新聞系の電波メディアの先導師 |
| 齋藤守慶 | 関西が生んだ優れた民放経営者 |
| 髙橋一夫 | 民放ラジオ局を創った男 |
| 後藤亘 | 民放FMを開花させた男 |
| 徳田修造 | 日本初の衛星ペイテレビを創造した男 |
| 第4章 電波行政・技術開発 | |
| 藤木栄 | 放送発展期の「電波監理局長」 |
| 石川晃夫 | 放送発展期の「電波監理局長」 |
| 野村達治 | 誇るべきNHKの放送技術者 |
| 高橋良 | 誇るべきNHKの放送技術者 |
| 吉田稔 | 誇るべき民放の放送技術者 |
| 河内山重高 | ローカル民放局の独創的技術・経営者 |
| 澤崎憲一 | 「日本のVTR」を創った男 |
| 森園正彦 | ソニーの放送機器を世界に広めた男 |
| 水野博之 | 「家電の松下」の技術リーダー |
| 廣田昭 | 歴史的名機「VHS」を開発・普及 |
| 松本誠也 | 「音」と「映像」のフロンティア |
| 林宏三 | カラーテレビ向上に貢献 |
| 第5章 番組ソフト・広告 | |
| 高橋圭三 | アナウンサーの中のアナウンサー |
| 黒柳徹子 | テレビメディアの「不死鳥」 |
| 吉田直哉 | 「スペシャル番組」の開拓者 |
| 阿木翁助 | ラジオ・テレビの大作家 |
| 澤田隆治 | お笑い番組大国・ニッポンの魁 |
| 植村伴次郎 | テレビ映画の開拓者 |
| 大橋雄吉 | ミスター・ビデオレンタル |
| 梅垣哲郎 | 電通の黄金期を築いた仕事師 |
| 大前正臣 | 日本のテレビ広告を創った男たち |
| 尾張幸也 | 日本のテレビ広告を創った男たち |
| 川端嘉幸 | 日本のテレビ広告を創った男たち |
| 山川浩二 | テレビCMのヒットメーカー |
| 第6章 イベント/スポーツ | |
| 豊田年郎 | 博覧会の大プロデューサー |
| 入江雄三 | スポーツ・ビジネスの開拓者 |
| 第7章 放送・広告年表 [堀之内勝一編] | |
| 第8章 通信・コンピュータ行政 | |
| 赤澤璋一 | 航空機・コンピュータ産業育成に貢献 |
| 平松守彦 | 日本のコンピュータを育てた男 |
| 下河辺淳 | 国土計画のグランドデザイナー |
| 曽山克巳 | データ通信自由化を陣頭指揮 |
| 守住有信 | 「テレコム3局」をつくった男 |
| 江川晃正 | 電気通信事業の近代化を促進 |
| 第9章 通信・コンピュータ事業 | |
| 真藤恒 | 電電公社最後の総裁・NTT初代社長 |
| 山口開生 | 日本のテレコム事業のトップリーダー |
| 小林宏治 | 「C&C」構想を世界に広めた男 |
| 三田勝茂 | 「日立のコンピュータ事業」を確立 |
| 山本卓眞 | 日の丸コンピュータ産業の指揮官 |
| 椎名武雄 | 日本IBMを創った男 |
| 第10章 理論・技術 | |
| 西澤潤一 | 「光通信」開発の父 |
| 猪瀬博 | 「情報技術」の思想家 |
| 菊池誠 | 日本のトランジスタ生みの親 |
| 大島信太郎 | 国際電気通信の泰斗 |
| 尾関雅則 | 「みどりの窓口」を成功させた男 |
| 唐津一 | 「モノづくり」の伝道師 |
| 白根禮吉 | 元祖ニューメディア |
| 第11章 ニュービジネス | |
| 皆川廣宗 | スーパーバードのリーダー |
| 中山嘉英 | JCSATのリーダー |
| 稲盛和夫 | 京セラから第二電電へ |
| 江副浩正 | 天才メディアプロデューサー |
| 山内溥 | 「任天堂」を世界の「Nintendo」にした男 |
| 西和彦 | ビル・ゲイツと競い合った男 |
| 北島義俊 | 印刷産業のトップリーダー |
| 鈴木和夫 | 印刷産業のトップリーダー |
| 大竹猛雄 | 元祖・日本のTSS |
| 石黒公 | 日本型CATV事業の推進者たち |
| 佐藤浩市 | 日本型CATV事業の推進者たち |
| 中村安雄 | 日本型CATV事業の推進者たち |
| 塚本芳和 | 日本型CATV事業の推進者たち |
| 岡田智雄 | パソコン通信ビジネスを確立 |
| 新山迪雄 | 新聞・雑誌の電子図書館を構築 |
| 松平恒 | 「明日のCATV」に賭けた男 |
| 坂尾彰 | 世界初のマルチメディアCATVを創造 |
| 佐野匡男 | 世界初双方向CATV実験者 |
| 神戸芳郎 | 専門多チャンネルTVの開拓者 |
| 第12章 21世紀へ向けて | |
| 成田豊 | 一人ひとりが何か一つの創造を成し遂げていける日本に |
| 第13章 総合年表+解説 [和久井孝太郎編] | |
| 第14章 監修者座談会 | |
| 塚本芳和・和久井孝太郎・堀之内勝一 | ロマンに賭けた男たちの歴史 |